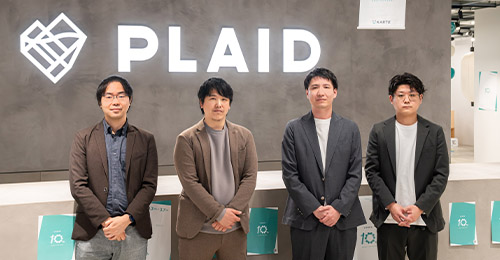課題
- GA4移行後の分析ノウハウやリソースが不足していた
- サイト全体での課題点が曖昧になり、改善の方向性が見えにくくなっていた
効果
- GA4の基礎知識と体系的な分析手法を習得し、分析の内製化が進んだ
- 施策効果を数値で検証できる評価軸を確立した
- Webサイトの戦略的活用意識と改善に向けた部門間連携が向上した
日本農薬株式会社について
日本農薬株式会社(以下 日本農薬)は、1928年に創業し、日本初の農薬専業メーカーとして、農薬の製造・販売を主軸に医薬品・動物薬・木材用薬品など、多岐にわたる分野で事業を展開してきました。現在は、国内のみならず、中南米・アジア・欧州・北米などに複数の拠点を有し、「病害虫・雑草診断アプリ」や「営農サービス提供事業者向けAPI」の開発など、スマート農業領域にも積極的に進出しています。主力事業である農薬分野においてタイムリーかつ的確な情報提供が必須であるとともに、事業の多様化とグローバル展開の進展により、情報発信の要となるWebサイトの役割がいっそう重要性を増しています。
お話を伺った方

日本農薬株式会社
管理本部 総務・法務部 総務広報グループ
横田 直也氏
日本初の農薬専業メーカーとして、長年にわたって事業を展開してきた日本農薬にとって、製品としての農薬の提供だけでなく、適切な製品選択や使用方法といった情報の提供も、重要な社会的責務となっています。
そうした思いのもと、日本農薬ではWebサイトによる迅速かつ適切な情報提供を実施するべく、メディックスの支援を受けながらデータ解析の内製化を進めてきました。この取り組みを牽引したのが、管理本部 総務・法務部 総務広報グループでWebサイト運営を含めた情報戦略を担う横田直也氏です。今回は横田氏に、内製化プロジェクトの経緯や成果、今後の展望などについてお話を伺いました。

安全で安定的な食と豊かなくらしを守るために
― 日本農薬の事業とそのミッションについてお聞かせください。
現在、世界各国で食糧不足の傾向が続いており、食料の安定供給はグローバルな課題となっています。日本においても、農作物の不作や米不足などが報じられるように、必ずしも安定しているわけではありません。
そうした中で、農薬の果たす役割は非常に重要です。作物に被害を与える病害や害虫を放置すれば、本来収穫できるはずだったものが失われ、安定した食料供給が難しくなってしまいます。農薬の適切な使用は、収穫量の維持・向上だけでなく、品質の確保にもつながり、持続可能な農業経営と食料の安定供給を支えます。つまり、農薬は単なる製品ではなく、人が生きるために不可欠な農業という営みに欠かせない技術であり、日本農薬が社会に貢献するための重要な手段なのです。私たちは日本初の農薬専業メーカーとして農業の現場を支えながら、食の安全と安定確保という重要課題に対し、常に真摯な姿勢で向き合っています。
― 近年は、農薬だけでなく多様な資材の提供やスマート農業にも取り組まれていますね。
日本における食料生産には、もう一つ、少子高齢化に伴う農業の担い手不足という大きな課題があります。これを解決するには、生産法人化や農業経営の集約化などによって、より少人数で広大な農地を効率的に管理・運営する必要があります。「食べ物は外国から輸入すればいい」という人もいますが、そう簡単なことではありません。輸入に依存しすぎる状態では、有事の際の国際的な供給リスクに対応できなくなる可能性があります。食料安全保障の観点からも、国内の農業は一定規模で維持・保全し、国の基幹産業としてしっかりと守っていく必要があるのです。
そのためには農作業の高度集約化と効率向上がこれまで以上に求められ、限られた人員で安定した生産を維持するために、農薬だけでなく多様な技術や資材の活用が欠かせません。とりわけ「スマート農業」と呼ばれるデジタル技術の導入と活用は、農作業の効率化・高度化を飛躍的に進めるものとして大きな期待が寄せられています。
日本農薬でも、長年にわたる農薬事業で培った知見・ノウハウを活かしつつ、AI病害虫・雑草診断アプリやドローンを活用した圃場診断・防除支援などの営農支援サービスへの外部連携を可能にするAPI提供など、最先端技術を取り込んだソリューション開発に取り組んでいます。スマート農業分野においても、安全で安定的な食と農に役立つ価値を提供していきたいと考えています。
多様化するステークホルダーに迅速かつ適切に情報を届けたい
― そうした状況下で、Webサイトの目的や役割をどのように位置づけていらっしゃいますか。
まずコーポレートサイトについては、日本農薬の組織や事業に関するさまざまな情報を、あらゆるステークホルダーに対して発信する”要”として捉えています。目的としては、営業や採用などの直接的な成果につなげることはもちろんですが、社会的影響力の大きい農薬という商材を扱う企業として、研究開発力や環境配慮の姿勢などを積極的に発信し、各方面からの信頼を得ることを重視しています。とはいえ、顧客や取引先はもちろん、投資家や株主、研究者、求職者や学生、行政機関、業界団体など、サイトを閲覧する人によって、求める情報も違えば、私たちから提供したい情報も異なります。そこで、Webサイトの運営においては、それぞれの方々に求められる情報、閲覧していただきたい情報を迅速に提供できるよう、コンテンツを拡充し、導線も含めて整理することを心がけています。
特に農薬に関しては、国が使用方法などについて厳格な規制を設けており、掲載すべき情報も細かく定められています。さらに新製品はもちろん、200品目を超える従来品についても、他の農作物や病害虫への効果が新たに確認された場合など、数ヶ月から1年ほどのサイクルで情報の追加・変更が発生するため、その管理や更新作業は非常に煩雑になりがちです。当然ながら使用者にとっては、自身が使用する薬剤に関する最新情報をできるだけ迅速かつ正確に入手したいというニーズが強く、当方のWebサイトへの期待もそこにあります。
― Webサイトの運営・改善について、どのような課題をお持ちだったのでしょうか。
多様な利用者に迅速かつ適切な情報を届けるため、当社では以前からGoogle Analyticsを活用してログ解析に取り組んできました。気になる数値を抽出し、全体の傾向を把握することまでは一定の精度で対応できていたと思います。
しかし、Google Analytics4(GA4)への移行により機能が大幅に拡張され、社内の限られたリソースでは十分に使いこなすことが難しくなってきました。インターネットで情報を調べながら分析を試みても、それが正しいのか自信が持てず、必要な情報をピンポイントでしか取得できないことにストレスを感じていました。
たとえば、ある薬剤について情報を閲覧している人がいたとして、関連する農業技術や周辺情報などを想定し、ニーズの一歩先を行く情報を提供できれば、利用者の利便性を高められるでしょう。しかし、その仮説を検証する方法を探して分析するのには時間がかかり、できたとしても個別での施策に留まっていました。その結果、サイト全体での課題点が曖昧になり、改善の方向性が見えにくくなっていました。
属人的な仮説検証や部分的な改善に留まらず、Webサイト全体の持続的な改善へと変革するには、GA4を体系的に習得する必要がある。その考えのもと、組織横断のワーキングチームを立ち上げ、GA4を活用して「何を分析したいのか」、「どのような体制で進めるべきか」、そして「どのような支援が必要なのか」などについて、社内で議論するところからはじめました。

営業も交えて要件定義、きめ細やかな提案に感じた実現可能性
― ワーキングチームの体制や参画メンバーの構成について教えてください。
プロジェクトについては管理本部の総務・法務部が主管となり、国内営業本部にもプロジェクトの初期段階から参画してもらい、共同で推進する体制を整えました。以前の調査で、当社のWebサイトに訪れるユーザーのうち、製品情報の閲覧者が全体の半数以上を占め、既存顧客だけでなく潜在層からのアクセスも多いことがわかっていました。 Webサイトにおける情報提供の精度や利便性が営業活動に直結し、営業部門にとって営業活動に欠かせない重要なメディアであることは明らかです。そこで、営業効果を意識した情報設計やアクセス解析の方針を策定するためにも、営業部門が直接的に関与することが必要だと考えたのです。
サイト全体を管理する総務・法務部の視点に加え、営業効果の向上を目指す営業担当者の視点も取り入れながら、当社として実現すべきアクセス解析のあり方について丁寧に議論を重ね、要件を整理していきました。 そのうえで、目指す解析環境の構築には外部の専門的な支援が不可欠であるとの判断に至り、メディックス社に正式に依頼する運びとなりました。
― メディックスにご相談されたご経緯や、ご依頼を決断されたポイントについてお聞かせください。
以前から、コンテンツ作成の効率化と管理体制の改善に向けて、当社ではシステム会社の協力のもとCMSを導入し、運用を進めてきました。当然ながら、分析とコンテンツ制作の両輪をうまく回すためには、システム会社やCMSとのスムーズな連携が不可欠です。そこでシステム会社に対して、信頼性が高く連携可能なパートナー企業の推薦を依頼したのです。それが2024年8月のことです。
複数の企業をご提案いただき、各社と丁寧にヒアリングを重ねた結果、当社が重視する「アクセス解析の内製化」という要件に対して、的確かつ誠実な提案をいただけたメディックス社に正式に依頼することを決定しました。
最終的な決め手となったのは、分析やスキルレクチャーに留まらず、実行フェーズや検証まで継続的に支援いただける体制が整っており、内製化の実現が確実に見込めると判断できた点です。ご支援内容も、広範な知見を備えながら要点を押さえた的確なものであり、費用対効果の高さも大きな魅力でした。また、新年度開始となる4月1日からの本格的な分析始動に向け、2025年3月末までに体制を整備したいという当社の要望に対し、具体的かつ詳細なスケジュールをご提示いただけたことは、実行可能性に対する強い信頼につながりました。
実感が伴う講習会とサイト分析で、体系的な分析手法を把握
― 内製化までに講習会を経て、サイト概況・課題の分析を行いました。どのように評価されていますか。
いきなり分析からはじめず、まずは当社の社員向けに予備知識として、GA4の基礎的なデータの見方やレポート作成に関する講習会を開催いただけたのは、サイト分析の理解を深めるうえでたいへん役立ちました。講習会には ワーキングチームのメンバーである総務・法務部、国内営業本部、そしてスマート農業推進部から計8名が参加したのですが、自社のGA4管理画面を使った実践的な内容だったことから、現場での活用イメージが湧き、習得度が一気に高まったと感じます。もともと自己流ながらもサイト分析に取り組んできたこともあり、疑問や知りたいことが大量にあったようで、質疑応答が予定時間を超える場面もありました。講習会の時間外でも、問い合わせへの丁寧な対応をしていただき、大変ありがたく思っています。
サイトの分析については、全体の概況分析で課題の”種”を見つけ、課題分析で当該の課題を深堀りするという二段構えの進め方に、非常に納得感がありました。それまでの分析は「知りたいことを個別に知る」という、いわばツギハギ的なものだったのですが、メディックス社の分析は基礎的な数値から全体感を捉え、個別の課題を検証するという、まさにお手本のようで、「体系的な分析」の意義と手法を実感をもって理解することができました。最終的に改善案のご提示までいただき、それが具体的なアクション施策につながっていたことも「分析によるサイト改善の実効性」を実感しました。
― メディックスによる伴走支援について、どのように評価されていますか。
まず、しっかりとした進行管理について非常に満足しています。そもそもご支援をお願いした背景には、Webサイトの関連業務について人的リソースが不足しており、プロジェクトに専念できる体制が整っていないという事情がありました。そのため、どうしてもこちらからの連絡が滞ったり、作業が後回しになったりして、進行に遅れが生じることも少なくありませんでした。しかし、その都度、丁寧にフォローしていただき、根気強くサポートしてくださったことに本当に感謝しています。
さらに、講習や分析フェーズを経て、私たちの実践段階に入ってからも、”かゆいところに手が届く”きめ細やかな支援をいただき、安心感を持って取り組むことができました。専門家に気軽に相談できることが、継続的なチャレンジを後押しする心の支えになっていることは間違いないと思います。
約3ヶ月間で分析の内製化を実現し、マインドセットにも大きな変化
― 最たる目的であったサイト分析の内製化について、どのように評価されていますか。
2024年10月から準備を開始し、12月に講習会の実施、翌年3月までにサイト概況・課題分析を実施するという、本当に短い期間でしたが、求めるレベルまで分析のスキルを習得できたことに満足しています。もちろん、まだ学ぶべきことは多くありますが、基礎が身についたことで、今後は実践によって自立的にスキルアップできるでしょう。そして、Webサイトを担当する総務広報グループだけでなく、国内営業本部、スマート農業推進部から募ったメンバーの成長も楽しみです。現場や市場に近いところでサイト分析ができるようになったことで、効果のある施策や改善がスピーディに実施され、それがデータドリブンな事業活動を前進させるものになると確信しています。
その意味で、今回のワーキングチームでスキル獲得以上の成果として認識しているのが、「Webサイトを戦略的に活用する」というマインドセットです。私自身、プロモーション業務には長らく携わってきましたが、Webサイトという自社メディアを含め、広告や宣伝が事業にどの程度貢献したのかを定量的に測定することの難しさは実感しています。
特にBtoB商材の施策について「売上に貢献した」という手応えを得るのは容易なことではありません。だからこそ、自分たちでサイト分析ができるようになったことは、「自ら企画・実行した施策の効果を数値で検証できる」という点において大きな意味があります。そのプロセスを通じて、自分たちの仕事を客観的に評価し、結果を踏まえて次の施策を考え、実行するという、真の意味での「自走」が実現することを期待しています。
― 自社でサイト分析の内製化が始まって数ヶ月が経ちましたが、手応えはいかがですか。
スタートしてまだ間もないため、具体的な事例をご紹介するには至っていませんが、分析による効果や現象の可視化が、他の部門とのコミュニケーションにおいても大変有用であることを実感しはじめています。Webサイトのコンテンツ作成は基本的に各部門に委ねられていますが、主管である私たちからの視点で全体を見渡すと、情報の過不足や導線などの課題が見えてきます。そこで、感覚的な指摘だけでなく、分析に基づく数値データを根拠として示しながら改善提案を行えば 、担当部門と目線を揃えた上で施策を議論することができると考えています 。そして、個別施策だけでなく、「日本農薬として何を伝えたいか」という視点を共有しながら、重点的に情報量を増やすべきコンテンツ領域についても共通認識を持つことができ、 分析による可視化は、社内の合意形成や方針策定にも大きく貢献するという手応えを感じています。
持続的なサイト改善サイクルの構築、グローバルサイトの改善にも着手
― 日本農薬のWebサイト運営および情報戦略についての展望をお聞かせください。
まずは当面の目標として、あらゆるステークホルダーに対して適切な情報をタイムリーに提供できるよう、Webサイトを戦略的なメディアとしてブラッシュアップしたいと考えています。これまで懸案だった分析の内製化と各部門とのコンテンツ連携が体制として整い、動き始めたので、早々に加速させていきたいですね。特に誰もが容易にコンテンツを作成できるCMSでは担当者によって更新頻度が異なり、情報の過不足が生じていたため、あくまで「分析結果を指標とした」コンテンツの適正化と整理を実施していきます。その結果、単に製品情報を届けるだけでなく、それに付随する関連情報や知見もあわせて提供することで、それぞれの閲覧者にとって利便性の高いWebサイトとなることが理想です。
そして、スマート農業の事業においても、広報や普及活動にはデジタルマーケティングが必須なので、分析について学んだことをしっかりと活用していきたいと考えています。特にスマホアプリ「レイミーのAI病害虫雑草診断」は、農業関係者が最も使うアプリの1つでもあり、一般の方のダウンロードも多く、日本農薬に興味をもっていただくきっかけにもなっています。ここを起点にどう導線を引くか、SNSなどWebサイト外とどのように連携するか、試行錯誤しながら考えたいと思っています。
そして、事業として売り上げの7割を占める海外向けの英語版サイトについても、そろそろしっかりと手を入れたいと考えています。海外における事業形態が日本と異なり、取り扱う情報が少ないために提供する情報は少なめでしたが、近年は都市化地域を含む海外市場で投資が活発となり、IRに関する情報提供が求められていることも実感しています。誰がアクセスしているのか、何を知りたいのか、分析によって明らかになったニーズに応え、コンテンツを充実させていきたいと考えています。
― メディックスに対する期待や要望などがあればお聞かせください。
私たちの事業ドメインである農業は、1年という長いサイクルで動いているため、たとえスマート農業の事業であってもアップデートの頻度が緩やかです。そうした時間軸ゆえに、ITなどのテクノロジーに対するキャッチアップはやや苦手なところもあります。自走支援のプロジェクトは完了したとはいえ、専門的な知識を持つ相談相手としてサポートいただければ幸いです。
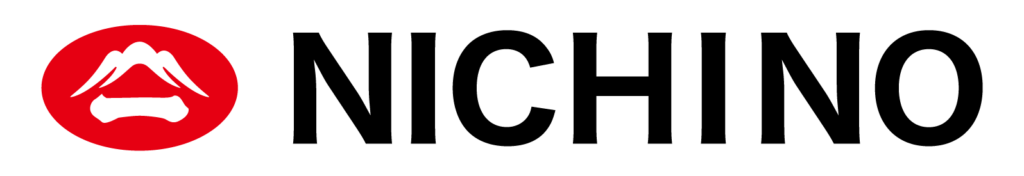
日本農薬株式会社
事業内容:農薬、医薬品、動物用医薬品、工業薬品、木材用薬品、農業資材などの製造業、輸出入業、販売業
設立:1928年11月
https://www.nichino.co.jp/